
昔はこんな薬もありました 3
~ 『アンテルミンチョコ』他 ~このシリーズでは内服ワクチンや市販されていた覚醒剤などを紹介いたしましたが、今回は(その3)として比較的近年まで生存していた (1)『アンテルミンチョコ』(2)『アンプル入風邪 薬』(3)『カルブンケン軟膏』の3点取り上げてみます。
1. アンテルミンチョコ
- 顕微鏡が発明される前の細菌学がこの世に生まれていない時代、細菌やウイルスの存在そ のものが概念に無かった昔には、諸々の病は体内の虫が悪さをするためと考えられておりました。
下記の明治初期の薬〔蘇生命親丹〕の効能書には様々な体内の虫とそれらが引き起こす病が描かれております。
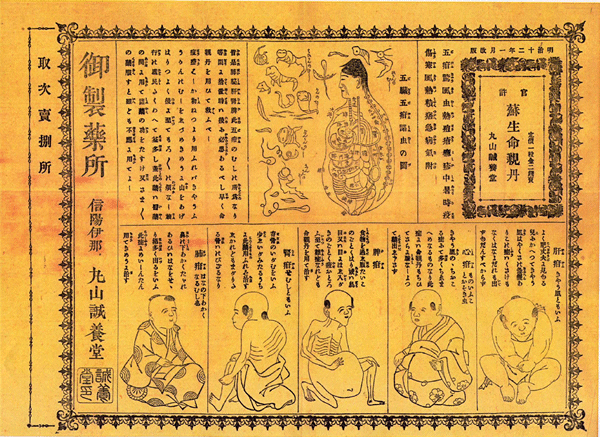
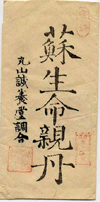




 寄生虫による病気はもちろん多種類あります(:右図の回虫、 蟯虫、條虫などの寄生虫の人体解剖模型は昔の保健室によく置いてあったものです。)が、この昔の薬の効能書のように、悪さをする多くのいろんな虫が体の中にいることは実際にはありません。
寄生虫による病気はもちろん多種類あります(:右図の回虫、 蟯虫、條虫などの寄生虫の人体解剖模型は昔の保健室によく置いてあったものです。)が、この昔の薬の効能書のように、悪さをする多くのいろんな虫が体の中にいることは実際にはありません。
しかしながら人糞を肥料にしていた時代、有機肥料や殺虫剤、農薬の発達、普及していない戦前~昭和20・30年代頃には日本の学童のほとんど90%近くは寄生虫に冒されておりました。
よって学校ではなかば習慣的に検便が行われ、いわゆる“虫下し”を飲ますことが行われておりました。
当時使われた様々な“虫下し”は後日、日を改めて御紹介いたしますが、今回は“虫下し”のなかでも異色とも言える『アンテルミンチョコ』を取り上げてみました。
自分も含めて最近の臨床薬理学などとは程遠いラテン語まで登場する古い時代の薬学教育を受けた薬剤師には懐かしい名前ですが、石榴(ザクロ)皮、海人草(カイニンソウ)、マクリなど昔の生薬学の教科書に登場した駆虫薬が“虫下し”の主流成分でありました。
ところがこれらの生薬成分の駆虫薬は煎じた生薬を服用すればもちろんのことひどくまずく、当然虫でさえ死ぬほどの味でした。 そこで中村化成産業という会社が“チョコに混ぜたらどうだ!”と考え日本で初めて作った虫下しチョコがこの『アンテルミンチョコ』です。
しかしながら当時は物資不足でまともなチョコレートは作れないため、ココアを砂糖でなくブドウ糖に溶かして製品とし、名前は対害虫=アンチヘルスミンからとって『アンテルミンチョコ』と命名したとのことです。
このコレクション入りの『アンテルミンチョコ』は全量7瓦で35円の製品で、次のことが書かれてあります。
有効成分 … 日本薬局方「サントニン」0.03瓦含有
海人草製剤「カイニン」及び石榴皮を主剤とし各種の栄養剤を配合してあります
効能 … 蛔虫、蟯虫、鞭虫、虫腹痛み等に良く効きます
特徴 … 本剤はお菓子のように食べやすく栄養にもなり駆虫率は高率です劣化していますが、扇の印の極印が見てとれます。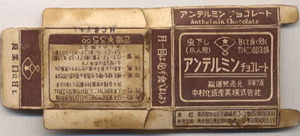

ウチの薬局にいた50歳代の薬剤師は子供の頃、この『アンテルミンチョコ』を食べ過ぎて視界がまっ黄色になった経験があるそうですが、某薬剤師会の副会長も御幼少の頃売り物の『アンテルミンチョコ』をいわば盗み食いしてバレて、強力な浣腸と下剤をかけられた貴重な経験をお持ちとのことです。
2. アンプル入風邪薬
- 効き目のある薬を国民、市民に提供することは薬剤師の大事な使命ですが、副作用、薬害の防止も大事な仕事です。
日本人の発明した簡単、手軽に飲めて、すぐ効きそうな感じがするリポ◎、オロナミン◎・・・等々のドリンク剤は薬好きのいそがしい日本人の体質、気質に合っており、現代でも市場の売上の高位を占めコンビニでも売られていますが、この『アンプル入風邪薬』も同じ発想で生まれたものです。
しかしながらあまりにも日本人の体質、気質に合いすぎたせいか乱用され市場から消え去った薬です。
正確には昭和40年(1965年)の冬の2月頃から過量摂取等によるピリン成分のショックによる死亡事故が相次ぎ、2月20日には大正製薬とエスエス製薬が販売を禁止、5月には当時の厚生省が製造の禁止を通達し、この世から消滅したものです。
このコレクション入りのアンプル入風邪薬は大阪道修町のメーカーが製造、奈良県の成光薬品工業が発売していた『かぜリートン内服液』という製品で1本150円です。
なおこの時代の世相は昭和39年にはスモン病が命名され、東京オリンピックが開催され、東海道新幹線が開業され、昭和42年には医薬品副作用モニター制度が実施され、また公害対策基本法案が閣議決定されております。アンプルはプラスチックアンプル製で主な成分は、 アミノピリン 200mgなどで用法用量は、“大人1日1回1本(30ml)内服”
マレイン酸クロルフェニラミン 8mg
リン酸ジヒドロコデイン 10mg
dl-塩酸メチルエフェドリン 50mg
カフェイン 50mg
適応症には、“かぜ熱、鼻かぜ、気管支炎や咽頭カタル、四季感冒、 扁桃腺痛”の他、“喘息、百日咳の咳”も書かれております。
同社のHP(http://www.asm.ne.jp/~seikou/history.htm )を見ますと、
 『かぜリートン』は昭和33年(1961年)に発売されたようです。
『かぜリートン』は昭和33年(1961年)に発売されたようです。
明治38年創業の同社は現在も各種配置売薬はじめ“何処にでもある「モノ」は作りません”をモットーに各種保健機能、栄養機能食品の製造も行っており、平成17年(2005年)には創業100周年を迎えた元気な奈良の地場製薬メーカーのひとつです。


3. カルブンケン軟膏
- 本項最後の御紹介コレクションが大正13年(1924年)に発売され昭和50年(1975年)に消滅した三共の『カルブンケン軟膏』です。
この軟膏は「カルブンケン」というものを25%、ホウ酸を5%含む軟膏で“よう(:廱ト書ク)”、 “疔(ちょうト読ム)”などに有効な薬でした。
“よう”はカルブンケル(Karbunkel)、“疔”はフルンケル(F-urunkel)とい いますが、この「カルブンケン」という名称は このあたりから取ったもののようです。
では「カルブンケン」とは何かといいますと効能書によりますと複方柴参エキス、桂皮末、タルクの混合物 を乾燥したものに植物性炭末、つまりは炭を混和した もので黒く、当然軟膏もまっ黒い色をしています。
別項で説明いたしますが民間薬、漢方薬のなかに “黒焼き”という製剤があります。 動物や植物を 密閉した容器内で、つまり酸欠状態で焼いたもので“霜(そう)”と同意語で、代表的なものに乱髪霜、猿頭霜や伯州散などがあり、現実に効果はあるのですが、その製剤としての意義や薬効薬理の解明など現代に至るも全く時代の流れから置き忘れられた存在といえる剤型です。
つまり「カルブンケン」の成分の植物性炭末は“黒焼き”“霜(そう)”の一種かと思われます。
一方大正4年(1915年)に東大の山極勝三郎らは家兎の耳にコールタールを塗り続ける方法で世界で初めて皮膚癌を人工的に作ることに成功、癌の解明、研究の発展に大きな貢献をしましたが、炭 →→ タール →→ 発癌性?? と単純に考えると・・・、あるいはこの軟膏がホウ酸を含むためか、いずれにせよ効き目があるにもかかわらずこの世から消滅してしまった薬です。
では、今回はこの辺で終わらせていただきます。


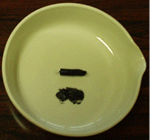
( 本項参考文献 )
田中 聡 著 「ハラノムシ、笑う」 河出書房新社
高橋 良忠 著 「近代漢方薬 ハンドブックII」薬局新聞社
©一般社団法人北多摩薬剤師会. All rights reserved.
190-0022 東京都立川市錦町2-1-32 山崎ビルII-201 事務局TEL 042-548-8256 FAX 042-548-8257
